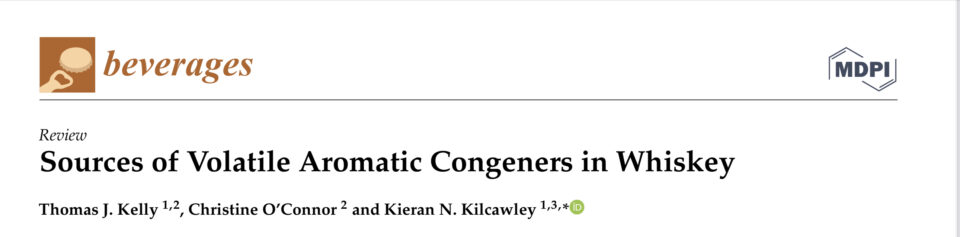ウイスキーにおける揮発性香味成分(コンジナー)の由来
要旨
ウイスキーの複雑で多様な風味は、穀物原料(マッシュビル)および製造工程の各段階(製麦、糖化、発酵、蒸留、樽熟成)に大きく依存する様々な反応によって生成されるコンジナーによって生み出される。そのため理論上、ウイスキーのコンジナープロファイルはその原料と製造工程各段階の特定のパラメータの総和であると言える。コンジナーのプロファイルは品質や真正性のバイオマーカーとして利用されてきた。しかし現在まで、特定のウイスキースタイル/タイプに関連するコンジナーの広範なプロファイリングや、銘柄内および銘柄間の変動性に関する十分な情報は公表されていない。特にアイルランドでは産業の近年の急拡大によりその傾向が顕著である。近年、抽出法、クロマトグラフィー、およびケモメトリクス手法の進歩によってコンジナーを抽出・同定する能力は飛躍的に向上している。そのため、特定のコンジナーが品質に及ぼす影響だけでなく、真正性のバイオマーカーとしての役割についても理解を深めるために、さらなる研究を行うことが不可欠である。
キーワード: ウイスキー、コンジナー、バイオマーカー、真正性、揮発性分析
1. はじめに
ウイスキー(whisky または whiskey)の製造には、水、穀物、酵母という3つの主要な原材料が用いられ、基本的には共通した工程に従う(本レビューでは特に断りのない限り whiskey の表記を用いる)。しかしスタイルや蒸留所ごとに操業手順やパラメータは大きく異なるため、最終製品には顕著かつ微妙な無数の違いが生じる可能性がある。例えば、穀物品種の選択、製麦方法、発酵条件、蒸留の工程・設計、熟成期間、樽の種類、熟成環境の選択といった要因は、いずれも製品の最終的な風味に影響を与え得る。【1】 さらにブレンディング(複数原酒の調合)はウイスキーカテゴリーの主要な製品形態であり、複雑さを一層増す要因である。こうした多様な要因の組み合わせにより、ウイスキーには多種多様で特徴的なフレーバーが生まれる。これは潜在的に香味に寄与する多数の化合物(一般に「コンジナー」と呼ばれる)の存在によるものである。ウイスキーに識別される主なコンジナーの化学的グループとして、アルコール類、エステル類、アルデヒド類、有機酸類、フェノール類、ラクトン類、テルペン類、タンニン類が挙げられる【1】。これらは製造プロセスの複数段階で生成され、ある段階でより多く生成されるものもあれば、別の段階で卓越するものもある。コンジナーの種類や濃度の違いは独特のフレーバープロファイルを生み出すだけでなく、スタイル/タイプ、地域、真正性に基づいてウイスキーを識別する手がかりにもなり得る。ウイスキーの真正性(オーセンティシティ)検証は、ウイスキーが高い人気を持ち高級品と見なされていることから、業界にとって常に重要な課題である。ウイスキーの偽造とは、瓶の再充填、偽物の製造、改竄などにより正規ブランドを模倣する行為であり、これによって業界のブランド価値、消費者の信頼、収益が損なわれる恐れがある【2】。2016年に欧州連合知的財産庁(EUIPO)が推計したところによれば、偽造品により欧州の蒸留酒・ワイン産業は年間13億ポンド(売上の約3.3%)の損失を被っている【2】。
既存のコンジナー・ライブラリー(香味成分データベース)に関する研究は、スコッチやバーボンについては広範囲に行われてきたが、特に新規参入が相次ぐアイルランドのウイスキーについてはほとんど発表されていないのが現状である。また、ウイスキー間の差異を明らかにしコンジナーのライブラリーを構築するために、これまで数多くのクロマトグラフィー分析や分光分析技術が用いられてきた。近年になって、自動揮発成分抽出法、包括的二次元ガスクロマトグラフィー(GC×GC)、高分解能質量分析、ケモメトリクス解析の著しい進歩により、ウイスキー中の微量コンジナーを抽出・特定する能力は飛躍的に向上した【1】。その結果、特定のコンジナーが官能特性や品質に与える影響をより深く理解し、真正性の検証に役立てることが可能になりつつある。
補足表1: ウイスキー中に識別される主なコンジナーの化学グループ
| 化合物グループ | 代表的な化合物例・香気特性 |
| アルコール類 (高級アルコールなど) | エタノール以外のアルコール成分。例:イソアミルアルコール(3-メチルブタノール)- バナナ様のフルーティで溶剤様の香り。 |
| エステル類 (脂肪酸エステル) | 有機酸とアルコールのエステル。例:酢酸イソアミル – バナナのような甘い果実香。 |
| アルデヒド類 | 第一級アルコールの酸化生成物。例:アセトアルデヒド – 未熟リンゴのような青い香り(高濃度では刺激臭)。 |
| 有機酸類 | 揮発性の低い酸性成分。例:酢酸 – 酢様の酸っぱい香り(高濃度で刺激味)。 |
| フェノール類 | ベンゼン環を持つ芳香族化合物。例:フェノール/クレゾール類 – 燻煙や薬品のようなスモーキーな香りを付与。 |
| ラクトン類 | 環状エステル(内エステル)。例:γ-オクトラクトン(ウイスキーラクトン)- ココナッツや甘い樹木香。 |
| テルペン類 | 植物由来の芳香成分。例:リモネン – 柑橘の皮のような香り。 |
| タンニン類 (エラジタンニンなど) | ポリフェノール類。渋味や苦味をもたらし、熟成中に分解してエラグ酸(渋味、苦味)などを生成。 |
2. ウイスキーの起源
アイルランドの修道士たちが11世紀に地中海への航海中にスペインのムーア人から蒸留の秘術を学んだと言われている【11–13】。当初、修道士たちはアクアヴィテ(aqua vitae) と呼ばれるハーブや精油を原料とした蒸留酒を作り、薬用として用いていた。ゲール語で「生命の水」を意味する「Uisce Beatha」(ウシュクベハ)という言葉はここに由来する【12】。アイルランドにおけるウイスキーの記録は1405年(クロンマクノイズ年代記に記載)に遡り、スコットランドで修道士ジョン・コーがその名を記した1494年より90年も前のことである【13】。17世紀には「uiskie」という短縮形が用いられ、1715年には「whiskie」に変化、1736年には現在広く使われる「whisky」の綴り(特にスコットランド産を指す)が定着した【14,15】。
1830年、アイリッシュマンのアイネアス・コフィー(Aenas Coffey)が連続式蒸留器(カフェ式蒸留器)を発明し、連続的かつ安価で効率的なウイスキー生産を可能にした。この技術は後にスコッチグレーンウイスキーの基盤となった。これに対抗して、アイルランドの蒸留業者たちは自国の製品をスコッチと差別化する必要に迫られ、マーケティング上の工夫として「whiskey」のスペルに「e」を加えるようになったとも言われている【14,16】。
19世紀後半、コフィー式蒸留器の普及による増産に加え、1880–1900年にフランスのブドウがフィロキセラ禍で壊滅した影響もあり、ウイスキーの人気は急上昇した【16】。しかし20世紀に入ると、アイルランドのウイスキーの生産と販売は数々の出来事により大打撃を受けた。1914年の第一次世界大戦では石炭や大麦が軍需優先となり、1916年のイースター蜂起とその後のアイルランド独立戦争でも生産に支障が生じた。そしておそらく最大の影響を及ぼしたのが、1920〜1933年のアメリカ合衆国における禁酒法である【16】。続く1939〜1945年の第二次世界大戦も状況に追い打ちをかけた。さらにアイルランド政府の保護主義政策(1919年以降1960年代までの高関税による自国産業保護策)は、安価な輸入品を排除する目的だったが、輸出にも障害となりアイルランド産ウイスキーの市場縮小を招いた【3,13】。
1960年代、アイルランドのウイスキー産業を立て直すための取り組みとして、1966年にジョン・パワー&サン社、ジョン・ジェムソン&サン社、コーク蒸留社が合併しアイリッシュ・ディスティラーズ社(Irish Distillers Group)が設立された。これに伴い、これらの旧蒸留所は閉鎖され、コーク県ミドルトンに新設の統合蒸留所が建設された。同時期に、工業成長と海外直接投資誘致を目的とした新たな政府戦略も展開された。北アイルランドのアントリム県にあるブッシュミルズ蒸留所も1972年にアイリッシュ・ディスティラーズ社に加わった【6,11】。この統合により生産量と販売量は増加したものの、アイルランド産ウイスキーのキャラクターはより画一化され、一般的にスコッチよりもスムーズで甘い風味を持つと評されるようになった【17】。その後、1988年にペルノー・リカール社がアイリッシュ・ディスティラーズ社を買収し、2005年にはブッシュミルズ蒸留所がディアジオ社に売却された。一方、1987年には島内でクーリー蒸留所(ロウス県)が操業を開始したが、これは当時他に稼働する蒸留所が無かったアイルランドにおいて数十年ぶりの新蒸留所であった。このクーリー蒸留所も2012年にビーム社(現ビームサントリー)に買収されている。
近年、アイルランドのウイスキー需要の高まり(特に米国市場で、2021年にはアイルランドウイスキーの売上が前年比16.3%増【17】)を背景に、アイルランド島内各地でクラフト規模から大規模生産に至るまで多数の新蒸留所が操業を開始している。スコッチの場合は(ボトリングを除き)ウイスキー製造工程のすべてが同一蒸留所内で行われることが法的に義務付けられているが【18】、アイルランドでは必ずしも全工程を同一施設で行う必要はない【10,18】。専門業者への一部工程のアウトソーシングが許容されているため、コスト削減や特定分野の専門知識による品質保証、さらには製品の多様化につながる利点がある。
アイルランド・ウイスキーの規制
アイルランドのウイスキーに関する技術規程(technical file)では、ウイスキーとは穀物と水を原料にマッシュ(もろみ)を仕込み蒸留した酒であると定義されている(スタイルやタイプによって細部は異なる)【10】。要約すると、アルコール分については合成または農業以外の由来のものを一切含んではならず、蒸留時のアルコール度数は94.8%(ABV)を超えてはならない。また、得られた蒸留液のフレーバープロファイルは原料に由来する風味を反映していなければならない。最終蒸留液は最低3年間の熟成期間を経なければならず、熟成は木製の樽(スコッチの技術規程とは異なりオーク材に限定されない【18】)を用いて700リットル以下の容量で行う必要がある。蒸留液に添加が許可されているのは水とカラメル色素(E150a)のみであり、後者はしばしば色調を整えるために使用される【10,19】。
各国は自国産ウイスキーを他国製と差別化するために、適切な製法や慣行を取り入れた法的なウイスキー定義を定めている場合が多い。そのため、これら規定に従わない製法で製造された酒は、その国や地域の「ウイスキー」あるいは正規品と名乗ることはできない。こうした法制度は生産者と消費者、および国家の税収を保護する役割を果たしている。
アイルランド産のウイスキーが蒸留酒として、かつアイルランド原産の製品として認められるためには、EU規則2019/787号による法的定義およびアイルランド・ウイスキー技術規程【10,20】の双方に準拠していなければならない。これら両文書には、アイルランド産ウイスキーに与えられた地理的表示(GI)保護についての詳細な要件も記載されており、アイルランド産ウイスキーは2016年に欧州委員会によりGI認定を受けている。GIステータスは品質や伝統の保証となるだけでなく、偽造品に対するさらなる保護手段ともなり得る。GIステータスを維持するため、アイルランド・ウイスキーの全ての種類はアイルランド島内で生産・熟成されなければならず、熟成を継続させるような容器に詰めたままで島外に輸出することは禁じられている。また、瓶詰めに関しては島外で行うことも許容されているが、その際にも官能特性が保持されるよう無菌水の使用や企業管理の下で行われる必要がある。GI認定の取得は、アイルランドの蒸留所を保護しウイスキー産業の文化を維持するとともに、ブランドを偽造品から守る枠組みを提供するものと考えられている【21,22】。
アイルランドはウイスキーの発祥地とみなすことができるが、その定義や規制は国により多少異なり、許容される製法や原料にも差異がある。これらの違いは各国の伝統や文化の多様性を示すと同時に、ウイスキーの風味やスタイルにもさまざまな変化をもたらす要因となっている。市場が拡大し続ける中で、規制の範囲内での革新的な製法や原料の例外も現れ始めている【10】。したがって、ウイスキー製品を継続的にモニタリングし、アイルランド産ウイスキーの多様性を特徴付けるコンジナーとその反応について理解を深めることはこれまで以上に重要である。これは風味形成に影響を与える工程をよりよく把握し、品質管理を行うとともに、不正防止にも役立つであろう【7,8,23】。
補足表2: ウイスキーの歴史における主な出来事
| 年(頃) | 出来事と影響 |
| 11世紀 | アイルランドの修道士が地中海で蒸留技術を習得し、**アクアヴィテ(生命の水)**を薬用酒として製造開始【11–13】。 |
| 1405年 | アイルランドでウイスキーに関する史上初の文献記録(クロンマクノイズ年代記)。 |
| 1494年 | スコットランドでのウイスキーに関する最古の記録(修道士ジョン・コーによる)。 |
| 1736年 | スコットランド産を指す「whisky」の綴りが一般化(それ以前はusquebaughなどと表記)。 |
| 1830年 | アイネアス・コフィーが連続式蒸留器を発明。以降スコッチグレーンウイスキーで広く採用され、生産効率が飛躍的に向上【14,16】。 |
| 1880–1900年 | フィロキセラ禍でフランス産ブランデーが壊滅し、代替としてウイスキー需要が急増【16】。 |
| 1914–1918年 | 第一次世界大戦により石炭・大麦が戦時優先となり生産縮小。 |
| 1916–1921年 | イースター蜂起および独立戦争で国内混乱、ウイスキー生産に打撃。 |
| 1920–1933年 | 米国禁酒法時代。主要輸出先での販売停止により、アイルランドウイスキー産業が大打撃【16】。 |
| 1939–1945年 | 第二次世界大戦。輸送や原料不足で生産困難に。 |
| 1966年 | アイリッシュ・ディスティラーズ社設立(パワーズ、ジェムソン、コークの3社統合)。ミドルトン新蒸留所で生産集約。 |
| 1972年 | ブッシュミルズ蒸留所がアイリッシュ・ディスティラーズ社に参加。国内主要蒸留所が一体化。 |
| 1987年 | クーリー蒸留所創業(数十年ぶりの新規蒸留所)。 |
| 1988年 | ペルノー・リカール社がアイリッシュ・ディスティラーズ社を買収(ジェムソン等ブランド継承)。 |
| 2005年 | ディアジオ社がブッシュミルズ蒸留所を買収(現在は2014年よりプロクシモ社傘下)。 |
| 2010年代 | アイルランド各地で新興蒸留所が続々誕生(クラフトから大規模まで)。特に米国市場の成長に伴い生産拡大。 |
| 2016年 | **地理的表示(GI)**として「アイリッシュウイスキー」がEU認定を取得【21,22】。欧州連合知的財産庁(EUIPO)が酒類偽造による年間損失を試算【2】。 |
3. アイルランド・ウイスキーの種類(スタイル)
典型的に、アイルランド・ウイスキーには4つの主要タイプがある。すなわち、モルト・ウイスキー、ポットスチル・ウイスキー、グレーン・ウイスキー、ブレンデッド・ウイスキーである【10】(図1)。モルト・ウイスキーは100%モルト大麦を原料とし、通常は銅製ポットスチルを用いたバッチ式(単式)蒸留で造られる【10】。「シングル」を冠する場合、それらウイスキーが単一の蒸留所で生産されたことを意味する。たとえシングルモルトであっても、異なる樽や異なる熟成年数の原酒を組み合わせてブレンドすることが一般的である(ただし全て100%モルト大麦を原料とし技術規程に沿った製法で作られたものに限る)【10,24,25】。
ポットスチル・ウイスキーはアイルランド独特のスタイルであり、製法自体はモルト・ウイスキーと類似するが、そのマッシュビル(穀物配合)が大きく異なる。具体的にはモルト化した大麦(30%以上)とモルト化していない生大麦(グリーン大麦、30%以上)を混合し、さらにオーツ麦、ライ麦、トウモロコシ等その他の穀物を5%以下加えたものを原料とする【25】。生のグリーン大麦を使用することで、香りと味わいに青リンゴの生/煮リンゴ様のニュアンスやスパイシーでクリーミーな口当たりが与えられる【10】。この未発芽大麦の使用は18世紀末のモルト税変動への対策として始まったが、近年ではモルト工程での過度な焙燥(キルニング)を避け、酵素が高温で失活するのを防ぐ利点もある【26】。
グレーン・ウイスキーはトウモロコシ、コムギ、ライ麦などを主原料とし、一般にモルト化大麦を約10%程度ブレンドして仕込みを行う(モルト大麦に含まれる酵素を利用し、デンプンから糖を取り出すため)【10】。ただしアイルランドでは外部から添加した酵素の使用も許可されているため、100%トウモロコシ等のグレーンを原料として製造することも可能である【10】。グレーン・ウイスキーは一般に、モルト・ウイスキーと比べて色が淡くライトな風味を持つとされる。その主な理由は、グレーン・ウイスキーの生産で連続式蒸留(カラムスチル)が用いられ、また麦芽の焙燥(キルニング)工程が無いことによる【27】。連続式蒸留(カラムスチル)はより高いアルコール度数(最大約94.5%)の蒸留酒を得ることができ、その過程でエタノールより揮発性の低いコンジナー(重い成分)の多くが取り除かれるため、得られるスピリッツの風味は軽やかになる傾向がある【10】。
ブレンデッド・ウイスキーは、上述の2種類以上のタイプのウイスキー、または同一タイプでも異なる蒸留所で作られた2種類以上のウイスキーをブレンドした製品である。限られた3種の伝統的スタイル(モルト、ポットスチル、グレーン)しかない中で、多様で独自の製品を生み出すためにブレンドの技術は極めて重要である【7,11】。ブレンディングによって既存ブランドの幅広いラインナップが可能となり、無数の組み合わせによる製品創出が実現する。ブレンドの技とは、構成要素となる原酒それぞれの香味を損なわず、あるいは高めつつ、全体として一体化した特徴的な官能特性を引き出すことである【10,11】。ブレンデッド製品ではレシピとして特定の種類のウイスキーを一定比率で組み合わせるが、実際には原酒のロットや樽ごとのばらつきに応じて調整が行われることが多い。同じ風味特性を維持するために、ブレンデッド・ウイスキーは単一のモルトやグレーンに依存しない。複数の原酒を組み合わせることで、時間経過による個別原酒の変化にも対応できる。どの蒸留所やブランド由来の原酒がブレンドに使われているかという知識は、消費者が購入前に製品の性格を把握し、ブランド忠誠心を高める手助けにもなっている。これは競争の激しい市場においてますます重要な要素である【7,11】。
補足表3: アイルランド・ウイスキーの主なタイプと特徴
| 種類 | 原料・製法 | 特徴(風味・性質) |
| シングルモルト・ウイスキー | 原料はモルト化大麦100%。単式蒸留(銅製ポットスチル)で2~3回蒸留。異なる樽や年数のモルト原酒を同一蒸留所内でブレンドして製品化。 | モルト由来の濃厚な麦芽風味。重厚でコクがあり、ブランドごとにフルーティさやピート香など特色が出る。 |
| シングルポットスチル・ウイスキー | 原料にモルト大麦(30%以上)と未発芽大麦(グリーンモルト、30%以上)を主体とし、他の穀物(オーツ麦・ライ麦・トウモロコシ等)を最大5%まで添加。単式蒸留で2~3回蒸留。 | アイルランド固有のスタイル。グリーン大麦由来の青リンゴ様のフレッシュな香りやスパイシーでクリーミーな口当たりが特徴。 |
| グレーン・ウイスキー | トウモロコシ、コムギ、ライ麦等を主原料に、一部モルト大麦(~10%)を加えて仕込み(または酵素添加)。連続式蒸留(カラムスチル)で高純度のスピリッツを得る。 | 淡麗で軽快な酒質。連続式蒸留による高いアルコール度数と穏やかな香味(穀物由来のほのかな甘み)。単体製品よりもブレンデッド用原酒として用いられることが多い。 |
| ブレンデッド・ウイスキー | 上記のモルト、ポットスチル、グレーン各ウイスキーの2種以上をブレンドした製品。または同タイプでも異なる蒸留所の原酒をブレンド。 | 多様な原酒の組み合わせにより、一体感がありながら複雑でバランスの取れた風味を創出。ブレンダーの技術によりブランド固有の安定した味わいを実現する。 |
4. ウイスキー製造工程とコンジナー
ウイスキーの香味成分(コンジナー)の違いは、使用される原料や製造工程上の違いに起因する。しかし、ある特定の香味差を生み出す単一の化合物または化合物群を特定することは、その製品の複雑性ゆえに極めて困難である【1】。製造工程上の些細な変更であってもコンジナー生成に影響を与え、工程がボトリングに至るまで動的な平衡状態で推移することを物語っている【1】。多くのコンジナー群は製造プロセスの複数段階で生成され得る(図2に模式的に示す)。究極的には、各工程が最終製品中のコンジナー濃度にそれぞれ固有の影響を及ぼす。つまり、ある成分は特定の段階でのみ生成されるものもあれば、複数の段階で生成・分解されるものもある。例えばフェノール類はピート(泥炭)で燻したモルトに強く関連し、製麦工程の焙燥(キルニング)で生成すると考えられており、ウイスキーにスモーキーで薬品的なフレーバーを与える【28】。しかしフェノール類は発酵や樽熟成の過程でも生成されることが知られており、ピーテッド特有の香味がこれらフェノール類だけに起因するのかは未解明の部分も残る【1,29】。このように、コンジナー分析は風味形成を探る上で極めて有用な指標ではあるが、個々のウイスキーに関与する全てのコンジナーを完全に突き止めるのは、多数の要因が存在し各成分の濃度や官能への影響が変動するため、事実上不可能に近いと言える。それに加え、極微量(痕跡レベル)で存在するコンジナーであっても、その濃度が臭覚閾値を上回る場合には遥かに高濃度で存在する成分より強い官能影響を持つこともある点に留意すべきである。すなわち、揮発性コンジナーはその濃度とにおい強度(におい活性度)の両方によって感知されるため、極めて低濃度でも香りに影響するものが存在する。そのため、揮発性の香味成分は閾値以上の濃度で存在して初めて人に知覚される【147】。
4.1 製麦(麦芽化)
ウイスキー製造の第一段階(主要穀物が大麦の場合)は**製麦(モルティング)**である。ここでは、大麦に発芽を開始させることで酵素を生成させ、穀物中のデンプンを糖に分解させる【25,30,31】。具体的には、植物ホルモンのジベレリン酸が胚に作用し、α-アミラーゼやβ-グルカナーゼなどの酵素合成が活性化されることで澱粉が分解され始め、さらに貯蔵タンパク質の分解によって発酵に必要なアミノ酸やペプチドも生成される。製麦は通常、約16℃の温水に大麦を浸漬し発芽を促す「浸麦」と、空気中で休息させる「通気工程」を交互に行い、2~3日かけて大麦の水分含有率を高め胚に酸素を行き渡らせることで開始される【11】。伝統的には、大麦をモルティング床の上に広げて空気乾燥させる手法が用いられてきた(現在も一部のスコッチ蒸留所で継続され、新たに再導入するケースもある)。しかし現在では、多くの蒸留所が製麦工程を専門のモルトスター(製麦業者)に委託しており、温風を吹き込む近代的設備で炭酸ガスを除去しつつ大麦を撹拌する方法が一般的である。
芽が出始めたところで、大麦は「キルン(乾燥炉)」で約24~48時間乾燥させる。これは大麦の完全な発芽を止め、糖分の浪費を防ぐためである(このキルン乾燥の工程で泥炭による燻煙を行えば、ピーテッド・ウイスキー用の独特なスモーキーフレーバーを付与できる)。キルニング(焙燥乾燥)の工程には大きく3つの目的がある。(i) 発芽の停止; (ii) アミノ酸と糖のメイラード反応(MR)を促進して色と風味を形成する; (iii) 含水率を約45%から4~5%程度に低下させ、後の発酵工程に必要な酵素を失活させず保存する、の3点である【32】。メイラード反応(MR)とは非酵素的な褐変反応であり、ウイスキーの重要な風味成分の形成に寄与する。例えば五炭糖(ペントース)を含む穀粒細胞壁成分がMRによって分解され、フルフラールやピラジン類などの香味成分が生成される【33,34】。MRは単一の反応ではなく、系のpHや温度により経路や生成物が大きく変わる一連の複雑な反応群である。一般に、MRは還元糖とアミノ基との間で進行し、熱エネルギーによって加速される。まず反応によりシッフ塩基と呼ばれる不安定な中間体(N-置換グリコシルアミン、炭素-窒素二重結合を持つ)が生成し、さらにアマドリ転位を経てケトソアミン(アミノケトン)へと異性化する【35,36】。このケトソアミン中間体がさらに反応を重ねて多様な生成物を生み出し、それらがさらに反応して幅広い風味化合物(コンジナー)を形成する。キルン内の温度が約120℃を超える場合にはカラメル化反応も進行する。カラメル化はMRとは異なり、糖の熱分解による反応であり、ジアセチル(2,3-ブタンジオン)のような揮発性香味成分を高濃度で生成する。ジアセチルはバタースコッチ様の甘い香りを有する化合物である【37–39】。この乾燥・焙燥工程を経て完成した大麦は「モルト(麦芽)」と呼ばれる。
補足表4: 製麦工程で生成する主な風味成分
| 成分 (例) | 由来 | 香りの特徴 |
| フルフラール | 製麦中のメイラード反応(穀粒中の五炭糖の熱分解) | アーモンドやナッツのような香ばしい甘い香り【33,34】。 |
| ピラジン類(例: 2-メチルピラジン) | 製麦中のメイラード反応(糖とアミノ酸の反応) | 焙煎麦芽やローストナッツのような香ばしい風味【33,34】。 |
| フェノール類(例: p-クレゾール) | ピート(泥炭)を焚いて麦芽を乾燥(燻煙)する工程 | 薬品様でスモーキーな香り(正露丸や煙臭)【28】。 |
| ジアセチル(2,3-ブタンジオン) | キルン内での高温カラメル化反応 | バターやトフィーのような甘い香り【37–39】。 (低濃度で良い香りだが、高濃度ではビール様の不快味となる) |
4.2 発酵
酵母発酵はウイスキー製造の中で最も重要な段階であるとも言われる。酵母によってエタノール(アルコール)が生成されるだけでなく、ウイスキーのフレーバーに関与する多数の代謝産物が生み出され、それらの一部はそのままコンジナー(香味成分)となり、また一部は後続工程で別のコンジナー生成の基質ともなるためである【11,54】。使用する酵母株の種類(あるいは混合)、発酵槽の設計、曝気の有無、発酵時間、仕込みウォート(麦汁)の組成、そして汚染バクテリアの有無といった要因は、いずれもコンジナーのプロファイルに影響を及ぼし得る【29,39】。麦汁の十分な冷却後に酵母を添加し、一般に20~32℃で発酵させる。可溶性糖が代謝されアルコール度数が約5~10%(v/v)になるまで発酵が続けられる【7,11,55】。
4.2.1 酵母と主要なコンジナー生成経路
異なる酵母“種”間、あるいは同種内の異なる酵母“株”間でウイスキーのコンジナープロファイルが異なるのは、酵母の代謝経路の違いによる。酵母はアミノ酸やタンパク質、糖類の利用法、さらには自己消化(オートリシス)における代謝産物生成が株ごとに異なるためである【56】。異なる酵母株を用いて新造スピリッツを製造した研究では、とりわけエステル類のプロファイルに顕著な違いが生じることが示されている【1,54,57,58】。蒸留用に開発された特殊酵母株は高アルコール濃度環境に耐えられるよう育種されている【59】。蒸留用酵母とは異なり、ビール醸造用やワイン醸造用の酵母(いずれも出発種は Saccharomyces cerevisiae)は高アルコール耐性や高速発酵よりも風味付与特性で選抜されている【60】。WaymarkとHillの報告によれば、ビール酵母を用いると新造スピリッツによりシリアル(穀物)様やフェンティ(硫黄・獣臭)様の特徴を付与し、一方でワイン酵母を用いると非常にライトでフローラルな香りになるという【1】。ウイスキー製造において複数種の酵母を混合して用いることも珍しくはない。混合酵母で発酵させた新造スピリッツではコンジナー濃度のバリエーションがより多様化すると考えられている。また、乾燥酵母(ドライイースト)と生きた状態の酵母(液体イースト)の違いによっても硫黄化合物の生成量に差が生じることが示されている【61,62】。
発酵条件も酵母の代謝に影響を与え、生成される副次代謝産物の比率、ひいては生成されるコンジナー組成に影響する【54】。したがって、発酵条件を変更することで特定のコンジナーの増減をある程度コントロールすることが可能である【39,63–65】。酵母発酵はエタノール生産のため厳密には嫌気条件下で行われるものの、発酵中の酸素は酵母にとって重要な役割を果たす。酵母が脂肪酸やステロール(細胞膜成分)を合成するには酸素供給が必要なためである【66】。十分な酸素がなければ酵母による脂肪酸・ステロール合成は制限される【11】。酵母の増殖初期における好気的条件は高級アルコール(C2以上のアルコール)やエステルの生成に大きく影響し、これはクラブツリー効果として知られる【67】。酵母は高濃度の糖環境下では好気条件でもアルコール発酵を行うことができる。一般に、高温かつ酸素が豊富な条件で酵母増殖を促すと高級アルコール類の生成が増加しエステルの生成は減少する傾向があり、酵母増殖が抑制される条件では逆の傾向となる【68】。これは、酵母が細胞機能や増殖のためにより多くの内部脂肪酸を消費し、さらにその目的でアセチルCoA需要が増大してエステル合成に回せるアセチルCoAが減少するためと考えられている【69】。同じ条件に対する応答は酵母株ごとに異なるため、発酵条件と酵母株の組み合わせ次第で醪(ウォッシュ)の風味、ひいては最終スピリッツの風味が変化し得る【7】。中鎖脂肪酸(C6程度)のような脂肪酸は酵母増殖時に用いられたり膜合成に利用されるため、これらの挙動もコンジナー生成に影響を与えるが、高温での発酵では酵母が内部脂肪酸をより多く消費することも高級アルコールとエステル生成のバランスに影響する【68,69】。なお、発酵中に酵母自身が自己融解(オートリシス)を起こすと、細胞内の物質が放出されて風味に影響することもある。このように二つとして同じ発酵は存在せず、酵母株や条件の違いが洗醪(ウォッシュ)の風味、ひいては最終スピリッツの香味に影響を及ぼす可能性がある【7】。
4.2.2 発酵における主要なコンジナー
発酵段階で生成する香味成分には様々な種類があるが、その中でも特に重要なものの一つがvicinal diketones (VDKs) と総称されるケトン類である。これは発酵産物として生成するジケトン(2つの隣接したカルボニル基を持つ化合物)で、ビールやスピリッツにおいて芳香を左右する重要成分である【46】。代表的なVDKとしてジアセチル(2,3-ブタンジオン)とアセチルプロピオニル(2,3-ペンタンジオン)が挙げられる。これらは発酵中に生成しうる成分で、バタースコッチのような強い芳香(ただし過剰だと不快とされる香り)に関与する【38,39】。ジアセチルおよびアセチルプロピオニルは酵母のアミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生合成経路中に排出される中間体であるα-アセトヒドロキシ酸(ジアセチルはα-アセト乳酸、アセチルプロピオニルはα-アセトヒドロキシ酪酸)の酸化的脱炭酸反応によって生成する【46】。生成したジアセチルはさらに脱炭酸されてアセトイン(3-ヒドロキシ-2-ブタノン)となり、さらに還元され2,3-ブタンジオールになる。またアセチルプロピオニルは還元されて2,3-ペンタンジオールになる【11,83,93,94】。ジアセチルは発酵中ごく微量しか生成しないことが多いものの、その香りのしきい値(閾値)は低く、スコッチグレーンウイスキーでは0.1 ppm程度と報告されている【38,95】。
酵母は発酵開始時に増殖のため酸素を必要とするため、その間に生成した高級アルコール類の一部は酸化されてアルデヒドとなり、さらに短鎖の有機酸へと変換されうる。また、大麦由来の脂肪酸(リノレン酸、リノール酸、オレイン酸、パルミチン酸など)が麦芽中のリポキシゲナーゼ酵素の作用で酸化され、アルデヒドを生成することもある【75,96】。例えば、発酵原料の麦芽由来のジメチルスルフィド(DMS)が酸化されてジメチルスルホキシド(DMSO)となり、発酵中に酵母により再びDMSへ還元されるケースなどが挙げられる【75】(DMSは煮干しやコーン缶様の香りを持つ揮発性硫黄化合物)。このようにアルコールのアルデヒドへの酸化は平衡関係にあり、発酵生成物中のアルデヒド濃度が高い場合には、ウイスキー製造プロセスの変動や特殊条件の反映である可能性が高いとも考えられる【38】。アルデヒドは中間生成物であるため、例えば発酵が不完全に終わった場合には高濃度に残留する傾向がある。実際、Scotchウイスキー(アルコール度数29.3–34.0%まで減圧蒸留した中間体)を調査したところ、アルデヒド濃度が高いことが報告されている【38】。アルデヒド類は個々に香り特性が大きく異なる。例えばヘキサナールは青臭い草の香り、トランス-2-ノネナールは段ボール様の香り、トランス-2-オクテナールは金属的かつキノコやおが屑のような香りを持つとされる【7,11,97】。
発酵で生成される極めて重要なアルデヒドにアセトアルデヒドがある。これは酸化由来ではなく、酵母がピルビン酸を脱炭酸してエタノールを生成する経路の中間体として生じるか、あるいはエタノールを部分酸化して生成する(酵母のアルコール脱水素酵素による)【98】。アセトアルデヒドはしばしばリンゴ様の爽やかな香りと関連づけられるが、高濃度では刺激臭となるため発酵や蒸留中にも注意深くモニターされる【99】。アセトアルデヒドは反応性が高く、発酵・蒸留系中で硫黄化合物やアルコールと可逆的な付加反応を起こす【100】。例えばアセトアルデヒドはエタノールと縮合してアセタール(ジエチルアセタール、1,1-ジエトキシエタン)を生成する。ジエチルアセタールは閾値の低い(強い)香気を持ち、エーテル様・甘い・ナッツ様の香りと表現される【40】。他のアルデヒドも高級アルコールと反応して様々なアセタールを形成し、フルーティーなアロマを与える場合がある【75】。アセタール生成は、中間体として不安定なヘミアセタールを経て別のアルコールと反応し完結する可逆反応か、強酸下で不可逆的に起こるかの二通りがある【86】。中性条件下(ある程度アルコール度数が高くpHも高めの場合)のアセタール形成は可逆的である。したがってアルコール度数40~50%程度(多くのウイスキーの蒸留液がそうである)では、アセトアルデヒド全体の15~20%程度しかエタノールと結合せず、残りは遊離のアルデヒドとして存在することになる【80】。そのため、アルコール度数の高いスピリッツでは長期熟成後でも遊離アルデヒド濃度がアセタール形成によって大きく減少することはなく、むしろ酸性が高い蒸留液のほうがアセタール生成が進みやすい【80】。
発酵では硫黄化合物も生成する。特に重要な反応は、仕込み麦汁中の硫酸塩イオンの還元(酵母による硫酸塩呼吸)と、酵母内でのシステイン・メチオニンの生合成過程である【61】。大麦由来のジメチルスルホキシド(DMSO)はキルニング中の酸化で生成したものであるが、発酵中に酵母がこれを還元してジメチルスルフィド(DMS)を再び生成する。発酵中に発生するCO₂によって大部分の硫化水素(H₂S)は揮散除去されるが、ウォッシュ中になお残留したH₂Sや硫黄成分は蒸留後のスピリッツの品質に悪影響を及ぼす【7】。H₂Sは酵母によってエタンチオールに転化され、さらに残存H₂Sと反応してメタンチオール(メチルメルカプタン)を生成する。メタンチオールは硫黄系成分(例えばDMSやジメチルジスルフィドDMDS、ジメチルトリスルフィドDMTS)の前駆体となる【75,101】。硫黄化合物は微量ではプラスに働く香味要素となり得るが、濃度が高くなるとネガティブな要因となる【44,61】。例えばいわゆるグレープフルーツ様メルカプタン(チオール)は10 ppb未満ではグレープフルーツジュースのような心地よい香りを与えるが、10 ppbを超える濃度ではゴムや硫黄臭のような不快な香りに転じる【12】。
補足表5: アミノ酸由来の高級アルコール生成
| アミノ酸 | 生成される高級アルコール(香気の特徴)【55,81,87,88】 |
| トレオニン (Thr) | 1-プロパノール(プロピルアルコール)。溶剤様でややフルーティー、甘い香り。 |
| バリン (Val) | 2-メチルプロパノール(イソブタノール)。ワイン様、薬品様でわずかに苦味を伴う香り。 |
| ロイシン (Leu) | 3-メチルブタノール(イソアミルアルコール)。かび臭を思わせる重いアルコール香やシードルのような発酵香。 |
| イソロイシン (Ile) | 2-メチルブタノール。エーテル様の揮発臭と脂肪様の重いアルコール香。 |
| フェニルアラニン (Phe) | 2-フェニルエタノール(フェネチルアルコール)。バラのようにフローラルで蜂蜜に似た甘い香り。 |
4.3 蒸留
発酵の終了時点では、ウォッシュ中のコンジナーは非常に薄い濃度で存在している。蒸留工程では、これら多数のコンジナーを濃縮すると同時に、一部の成分を除去する役割がある【102】。蒸留とは、液体混合物(ウォッシュ)を加熱して成分の揮発性の差に基づき成分ごとに留出させるプロセスであり、アルコール度数および特定のコンジナーを高める一方で、不必要な成分(溶解固形物や水など)を取り除くことが目的である。
4.3.1 ポットスチル蒸留
伝統的な単式蒸留では、通常2つの段階が別個の蒸留器で行われる。すなわち、一次蒸留を行う「初留釜(ウォッシュスチル)」と、二次蒸留を行う「再留釜(スピリットスチル)」である。初留釜は再留釜より大きく、目的は発酵液(ウォッシュ)を加熱し蒸留することである。エタノールは水より沸点が低い(約75℃付近で大部分が蒸発する)ため、加熱によりエタノールとその他の揮発性成分が先に気化し、蒸留器のネックを上昇して冷却器で凝縮し留出する【103】。初留の蒸留は留出液中のアルコール度数が約1%(v/v)程度に低下するまで行われ、得られた留出液は「ローワイン」と呼ばれ再留釜に送られる。二次蒸留(再留釜)では、蒸留開始直後に最初に得られる留出区画をフォアショット(初留分)と称する。フォアショットは刺激臭が強く、エタノールが高濃度で含まれるほかアセトン、メタノール、酢酸エチル、アセトアルデヒドなどの不快な軽質成分を多く含む。蒸留家は「曇り止めテスト(デミスティング)」などによってフォアショットを抜き去るタイミングを判断するが、多くの場合は時間経過を基準にしてカットする【11】。フォアショットの後に得られる留出区画がハート(ミドルカット)すなわちスピリッツであり、これだけが樽熟成に回される。最後に得られる留出区画はフェイント(後留)と呼ばれ、フォアショット同様に刺激臭はあるもののアルコール濃度はかなり低い。スピリッツからフェイントへのカット(留出の切り替え)は時間もしくは留出液中のアルコール度数で決定される【7,11】。カットから除かれたフォアショットとフェイントは次回のローワイン(初留液)に再投入され、再度蒸留される。このリサイクルにより、最終的な製品により濃厚な味わいが生まれるとともに、アルコールや香味成分の無駄が減らされる【12】。ほとんどのウイスキーは2回蒸留(初留釜→再留釜)だが、アイリッシュでは3回蒸留も珍しくない。三回蒸留は、一つのポットスチルで三度かけて行う方法(初留1回・再留2回)と、三基の蒸留釜を直列に用いる方法とがある。理論的には蒸留回数を増やすほど、より揮発性の高い成分(コンジナー)が除去されエタノール濃度が上昇する。蒸留器の数にかかわらず、重要なのは蒸留責任者(ディスティラー)が適切なタイミングで留出の各区画を切り替え、所望の香味成分を確保することである。切り替えが早すぎても遅すぎても、重要な芳香成分が失われたり、逆に不要な高揮発性成分や硫黄成分が持ち越されて最終製品の風味を損ねる可能性がある【101】。
単式蒸留において、アルコール蒸気はポットスチルの開放ネックを妨げられることなく上昇し、ラインアーム(蒸留器上部から伸びる横管)を通過して凝縮器に至り、液体に戻る。単式蒸留で得られるスピリッツは、その経路で大きな障害や再凝縮による精留を受けにくい分、連続式のカラム蒸留と比べ揮発性成分(コンジナー)の含有率が高くなる傾向がある(図5)【102】。ポットスチル蒸留では、蒸留器の設計パラメータ(蒸留釜自体の高さ、ラインアームの角度と長さ、冷却器の種類など)が最終的な生スピリッツ中のコンジナーの種類と濃度に影響を及ぼす【102】。例えばラインアームが上向きに傾斜しているとリフラックス(蒸気の冷却凝縮と液体への戻り)が最大化されるため、よりピュアでライトな(雑味の少ない)スピリッツが得られる。一方で下向きに傾斜したラインアームではリフラックスが起こりにくくヘビーなスピリッツとなり、アルコール度数は低いがコンジナー含量の多い留出液となる【7,11,12】。ラインアームが下向きの場合、蒸留釜内の液滴(ウォッシュ)が沸騰泡とともに上方へ吹き上げられラインアームに混入する「液抱き(ウォッシュキャリーオーバー)」も起こりやすく、これがフランやピラジン類(焦げた香ばしい成分)の多さとして現れる場合もある【33】。
4.3.2 連続式蒸留
バッチ式(単式)蒸留と連続式蒸留では、風味に影響する要因が異なる。連続式蒸留では装置や蒸留工程の効率が香味に直結しやすい(図6)【102】。連続式のカラムスチル(塔型蒸留器)には多段の蒸留プレート(篩板)が設けられており、塔内がいくつもの区画に分割されている【102】。各プレートには小孔が多数空いており、下部から上昇する蒸気が通過してその上の区画で液化し、そこでさらに再沸騰して次の区画へ上昇…という過程を塔頂まで繰り返す構造である。蒸気が上昇するにつれアルコール度数が段階的に高まっていき、塔頂付近で最高純度のアルコールが得られる。一方で使用後のもろみ(蒸留残さ)は塔底から排出される。蒸留塔の高さとプレート数はリフラックス(凝縮と再蒸発)の度合いに影響する。プレート数が多いほど凝縮→蒸発の繰り返しが増え、得られるスピリッツのアルコール度数が上がりコンジナー含有量は減少する【7,11】。連続式の塔内では、ある量のエタノールが蒸発すると同時に同量の水分が凝縮するため、蒸気相のアルコール濃度は常に上昇し、液相のアルコール濃度は常に低下していく仕組みになっている。したがって理論的には、再稼働のエネルギー損失を抑えるため一度平衡状態になれば装置を何日も連続稼働させることができる【7,12】。カラムスチルの幅や高さはスピリッツの純度や生産速度も左右する【103】。
連続式蒸留では、単式蒸留のようにフォアショット・ハート・フェイントといった明確な留出区画は存在しないが、実際には塔内の異なる高さから留出液を採取する「カット」に相当する操作が行われる。一般に上部で留出するほど高純度のスピリッツが得られ、下部(精留器の下部プレート付近、アルコール度数約10%)で留出するほど揮発性の低い成分を含んだスピリッツが得られる。通常、塔頂に近い留出を**初留(ヘッズ)相当、塔中部を主留(ハート)相当、塔下部を後留(テール)**相当として切り替える設計になっており、非揮発性で不快な成分が最終製品に混入しないよう第二留出点(ハートの終わり)の設定がなされる【103】。この留出切替の設定は、求めるコンジナーとその濃度に合わせて設計される。例えば初留カットを早めに行えば、ヘッズ成分の再循環が増え風味は軽くなる。逆にカットを遅らせれば、ヘッズ成分が減る代わりにより濃厚なテール成分が主留に混ざり、スモーキーなウイスキーではフェノール類を十分に取り込むことができる【7】。このように、ブレンデッド用のライトなグレーンスピリッツではカットを早めて不純物を極力排除し、ピーテッドモルトなど個性を強調する場合はある程度遅めにカットして重い成分を残す、といった調節が行われる。
補足表6: ポットスチル蒸留と連続式蒸留の比較
| 項目 | ポットスチル蒸留(単式・バッチ式) | 連続式蒸留(カラムスチル) |
| 蒸留方式 | バッチ式(単一ロットごとに初留・再留を行う) | 連続式(発酵液を連続供給し蒸留塔内で常時分留) |
| 蒸留工程 | 初留釜 → 再留釜(2回蒸留、場合により3回蒸留) | 一つの蒸留塔内で蒸留完了(複数の塔を連結する場合もあり) |
| カット(区画分け) | 時間・度数に応じて初留(ヘッズ)・心留(ハート)・**後留(テール)**に切り分ける | 塔内の異なる高さ(プレート)から留出を抜き出し初留/主留/後留を連続抽出 |
| 通常のアルコール度数 | 約70%前後(2回蒸留時、3回蒸留では80%超も) | 塔頂で最大94–94.8%(法定上限) |
| 風味傾向 | 低度数・単回蒸留ゆえ風味成分含有が多く重厚でオイリーな酒質。蒸留器形状で再留度を調整可能(背の高いポットや上向きラインアームでよりライトに)。 | 高度数・多段精留ゆえ風味成分含有が少なく軽快でドライな酒質。装置構造(塔の高さ・プレート数)で精留度が固定的に決まる。 |
| 主な用途 | 風味特性を重視したシングルモルト、シングルポットスチル、フレーバーの濃い原酒の生産(スコッチ・アイリッシュの伝統的手法) | 高い生産効率が求められるグレーンウイスキーや中性スピリッツの生産(大型連続プラントによる工業的手法) |
| その他の特記事項 | ポットの大きさ・形状、ラインアームの角度(上向き/下向き)、冷却方式(コンデンサーの種類)などでリフラックス量が変化し、香味に影響【102】。熟練した蒸留責任者によるカット操作が品質の要。 | 仕込み液の連続投入が可能で大量生産向き。定常状態での運転により品質が安定。特定成分(フェノール等)を取り込むため塔内カット点を調整する余地もある。 |
4.3.3 揮発性によるコンジナーの分類
蒸留段階でのコンジナーは、その揮発性(エタノールに対する相対的な揮発特性)に基づき、大きく3種類に分類できる。すなわち、エタノールより揮発性が高い(低沸点の)成分、揮発性が低い(高沸点の)成分、そしてエタノールとほぼ同程度の揮発性を持つ成分である【7】。ある成分の揮発性は通常その純物質の沸点に比例するが、蒸留過程ではエタノール濃度、極性、蒸気圧などにも影響される【7】。多くのコンジナーの見かけの揮発度は、蒸留中にエタノール濃度が変化していくことによって影響を受ける。特にエタノールと同程度の揮発性を持つ成分は、蒸留の進行に伴う系の極性変化などで相対的な揮発特性が変化する場合がある。例えば単式蒸留では、蒸留の後半にアルコール濃度が低下するにつれ、液体の極性が高まるため一部のコンジナーは時間の経過とともに相対的に揮発しやすくなる【7,11,103】。
蒸留の初留区画(フォアショット)には最も揮発性の高いコンジナーが集中する。典型的にはアセトアルデヒド、アセトン、酢酸エチル(エチルアセテート)、2-メチルプロパノール(イソブタノール)、3-メチルブタノール(イソアミルアルコール)、2-メチルブタノール、1-プロパノール、メタノールおよびいくつかのケトン類がフォアショットに多く含まれる【12,103】。フォアショット中に見られる一般的な分岐鎖アルデヒドには2-メチルプロパナール(イソブチルアルデヒド)、2-メチルブタナール(イソバレルアルデヒド)、3-メチルブタナール(イソペンチルアルデヒド)があり、ドライフルーツ様、モルト様(麦汁様)のノートを与える【7,40】。また多くのケトン類もフォアショットに存在するが、これらは一般に臭気閾値が高く香りへの寄与は小さいと考えられている【80】。しかしながらケトン類の中には重要な中間体や反応種となるものが多い。例えばβ-ダマセノンは不飽和の環状ケトンであり、他の化合物と相乗的に作用してフルーティーな香りを強調し青臭さを低減することが知られており、新造ウイスキーにおいてその重要性が指摘されている【75】。
多くのアルデヒド類やケトン類は蒸留の中間から後半の区画(ミドルカットやテール)にも存在する。これは分子量が大きくなるにつれそれらの化合物の沸点が上昇し、相対的に揮発しにくくなるためである【80,104】。一般に単式蒸留では、アルデヒド類と低級エステル類(短鎖エステル)の濃度は初留(フォアショット)からハートへのカット位置で決まる。これら成分は揮発性が高いため、カットを早めに行う(高い留出度数、例えば75–85%の段階でフォアショットを切り上げる)とハートに入り込む量が少なくなる。一方、高級アルコール類や有機酸類の濃度はハートからフェイントへのカット位置で決まり、これらは揮発性が低いため遅いカットほどフェイントに残らずハートに多く含まれる【40】。つまりフェイントを再投入する際に高級アルコールや酸が蓄積しやすくなる。スピリッツのカットポイント(留出停止度数)は、最終製品中のエステル類の種類と濃度にも影響を及ぼす。エステルは炭素鎖長により揮発性が異なるからである【29】。例えば、フォアショットからハートへのカットを早めに行い、約75–85%という高い留出アルコール強度でハートを開始すると、ハート部分のスピリッツには相対的に高級アルコール類や短~中鎖脂肪酸エステル類、酢酸エチルが多く含まれる傾向がある【40】。逆にカットを遅らせ留出度数が低くなると、より軽いエステルやアルデヒド類が多くハートに含まれる代わりに、高級アルコール類はフェイント側に残りやすくなる。ピーテッド麦芽由来のフェノール類は比較的沸点が高く後半まで残存しやすいため、ヘビーなスモーキーフレーバーを狙う場合にはカットを遅めに設定しフェノール類がハートに取り込まれるようにすることが重要である【7】。
4.4 樽熟成
蒸留工程で得られた無色透明かつニュートラルな新造スピリッツ(ニューメイク)は、多くのコンジナーを含んでいる。これらの成分の中には原料モルトから引き継がれたものや発酵・蒸留中に生成・濃縮されたものも含まれることは既に述べた【5,108,109】。**熟成(マチュレーション)**とは、新造スピリッツがより成熟してまろやかで円みのある製品へと変化していくプロセスであり、通常、加水によって度数調整した後に木製の樽に移し、最低でも3年間以上貯蔵することで行われる【10】。熟成に用いる樽は一般に容量200~700 L程度で、期間中にスピリッツと木材の間で様々な相互作用が起こる。
熟成中には樽内で3種類の反応が進行する。それは添加反応、相互反応、除去反応と分類される【112】。添加反応とは、樽材からスピリッツ中へ化合物が溶出し濃度が高まる現象であり、樽由来成分の抽出による香味付与がこれに当たる。相互反応とは、空気中の酸素が樽内に浸透することでスピリッツ中の分子同士、あるいはスピリッツ中の分子と樽由来の分子が反応を起こす現象である【12】。除去反応とは、蒸発・吸着・酸化などによって特定の成分が失われていく現象を指し、蒸留段階まで残っていた刺激性の強い化合物(ジメチルスルフィド、アクロレイン等)がこのプロセスで減少する【11,112–114】。
4.4.1 樽材の構成成分
ウイスキー熟成に用いられる木材は様々な高分子からなるが、中でも主要な4成分はセルロース、ヘミセルロース、リグニン、タンニンである【11,108】。これらのうちフレーバーに最も影響を及ぼすのはヘミセルロース、リグニン、タンニンであり、これら3成分は水には溶けやすくエタノールには溶けにくい性質を持つ【108】。セルロースは木材組成の約40~50%を占めるが、もっぱら他成分の運搬体として働き、自身は熟成中にほとんど溶出しない構造材である【7】。
ヘミセルロースはセルロースより熱に不安定な多糖類であり、グルコース、キシロース、アラビノースといったペントース(5炭糖)およびヘキソース(6炭糖)から構成される。ヘミセルロースは加熱による脱水反応を受けやすく、フルフラールや5-メチルフルフラール、5-ヒドロキシメチルフルフラール (HMF) などのフラノン類(フラルデヒド類)を生成する【7,11,75,115】。これらはロースト香、ファッジ(柔らかキャラメル)様、カラメル様の風味に寄与する。
タンニン類、とりわけ加水分解性タンニンであるエラジタンニンは熟成過程における重要な非揮発性成分である。これらはポリフェノールの一種であり、ウイスキーに苦味・渋味・青草様のニュアンスを付加するとともに、着色にも影響を与える【116,117】。一般に、色調を濃くする成分は分子量が大きく高度に共役した構造を持つため酸化されやすく、熟成中に色合いが変化する原因となる【118】。エラジタンニンおよびリグニンは硫黄臭の除去にも寄与する。Fracassettiらの研究では、ワインモデルでタンニンが揮発性硫黄化合物の生成を抑制することが示された【119】。Picarielloらは、この現象はタンニンが酸素消費を促進し二酸化硫黄の発生を抑制するためだと示唆している【120】。エラジタンニンは水に溶けやすく加水分解されやすいため、熟成中に速やかに分解してエラグ酸を生成する。このエラグ酸は熟成の進行に伴い濃度が増加する主要なポリフェノール化合物であり、最終的なウイスキーの風味に重要な寄与をすると考えられている【8,11,108,121】。エラグ酸にはフリーラジカルを捕捉し、ウイスキー内で過剰な酸化反応が進行して不要な生成物が生じるのを防ぐ効果(スカベンジャー作用)も確認されている【122】。
リグニンは不溶性の細胞壁高分子であり、加水分解するには共有結合の開裂が必要となる。Connerらの研究によれば、新樽、初回使用樽、2回目使用樽、使い古し樽の4種類のオーク樽を比較したところ、リグニン中のエーテル結合の大部分は酸による分解や加水分解に対しても安定であることが示された【123】。リグニンの分解は比較的ゆっくり進行し、熟成期間を通じて徐々に起こる。そのため、熟成年数の浅いスピリッツではエラジタンニン由来の成分が優勢だが、十分に熟成が進んだ製品ではリグニン由来の分解産物(低重合度のリグニンオリゴマー)が主体となってくる【108】。樽材から抽出される芳香族アルデヒド、フェノール類、ラクトン類、テルペン類などの化合物は一般に閾値が低~中程度であり、ウイスキーの重要な香気成分となる。これらの揮発性成分は、樽材の種類やシーズニング(乾燥熟成)の程度、さらには樽加工(トーストやチャーの度合い)などの要因によって量が影響を受ける【115】。
補足表7: ウイスキー熟成に関わる木材成分とその影響
| 木材成分 | 特徴・熟成への寄与 |
| セルロース | 木材の主成分(約40–50%)。高分子の繊維状成分で、熟成中は成分の運搬路として機能し、自身はほとんど溶出しない【7】。香味への直接的寄与は小さい。 |
| ヘミセルロース | 木材中の多糖類(約25%)。ペントース・ヘキソースから成り、熱で分解してフルフラール、5-メチルフルフラール、5-HMF等のフラノン類を生成【115】。これらはロースト香、カラメル様の甘い香り、ファッジ様の風味を与える。 |
| リグニン | 木材中の高分子(約20–30%)。熟成中にゆっくり分解し、芳香族化合物(バニリン、シリンガルデヒド、コニフェリルアルコールなど)を生成。バニラ香、ほのかなスモーキー香やスパイシーなニュアンスを付与する。熟成初期はエラジタンニン由来成分が優勢だが、熟成が進むにつれリグニン由来の成分比率が高くなる【108】。 |
| エラジタンニン(加水分解性タンニン) | オークに含まれる水溶性ポリフェノール(約5–10%)。熟成中に加水分解してエラグ酸を生成し、苦味・渋味・ハーブ様の風味を付与すると共に、抗酸化作用で硫黄系オフフレーバーの抑制に寄与する【119,120】。高分子で色を濃くする成分でもあり、熟成に伴う色調変化にも関与【118】。 |
4.4.2 オーク樽
ウイスキーの熟成には一般にオーク(樫)材の樽が使用される。オークは耐久性が高く液漏れしない一方で適度に酸素透過性があるという、熟成容器に理想的な特性を備えているためである【124】。アイルランドやスコットランドでは、アメリカ産バーボン樽(一度使用したもの)が大量に再利用されている。これは米国の法律でバーボンは一度使った新品のオーク樽で熟成させなければならないと定められているため、米国蒸留所から放出されるonce-usedのバーボン樽が大量に余ることによる【11】。これらバーボン樽は容量約200 Lで、伝統的なヨーロッパのウイスキー熟成に使われてきた約650 Lの大型オーク樽(シェリーバット等)に比べて単位体積当たりの表面積が大きい。そのため、小型樽の使用はスピリッツと木材の接触面積が大きく、熟成の進行が速まる傾向がある【11,12】。ヨーロッパ産のオークも広く使用されるが、新樽としてよりは中古のシェリー樽、ポート樽、ワイン樽の形で用いられることが多い。これらの樽は一般に約500 Lで、バーボン樽より比表面積が小さいため、セカンダリー熟成(後熟)に適している。表面積あたりの接触量が小さい分、香味の抽出は穏やかで時間依存的だが、繊細でバランスの良いフレーバーを与える傾向がある【125】。中古樽(シーズンド樽)は新樽ほど強烈な風味は付与しないものの、木材から抽出されるコンジナー(とりわけエラジタンニン由来物質)は依然豊富に含まれており、熟成中の酸化によってフェノール化合物へと変化していく。これにより、新樽より穏やかではあるが複雑でバランスの取れたフレーバーがスピリッツにもたらされる【10,11】。
アイルランド・ウイスキーのフレーバー多様性に潜在的に重要な要因の一つとして、熟成に使用できる樽材の種類がオークに限定されていないことが挙げられる(スコッチはオーク系の樽のみ使用可)【10,18】。そのためアイルランドでは、チェリーウッド(桜材)、アカシア材、クリ材など他の木材を用いたさまざまな試験熟成が行われている。Tarkoらは最近、オーク以外の様々な木材が持つ香味成分の可能性について報告しており、例えばクリ材にはオイゲノールやイソオイゲノールが高含有されていること、チェリーウッドやアカシア材にも特徴的な成分プロファイルがあることを指摘している【126】。
4.4.3 樽の内面焼きとコンジナー
樽熟成に用いるオーク樽は、その内側を強い炎で加熱・トースト(焦げ目付け)またはチャー(表面炭化)処理することがある(図7)。樽の加熱処理(トースティングやチャー)は、木材ポリマーを熱分解することで以下の3つの効果を狙って行われる。(i) 風味成分の抽出を高める; (ii) 木質由来の望ましくないフレーバー成分を分解する; (iii) 樽内面を強いチャーで炭化させ活性炭の層を形成する(木表面が割れて内側が黒く焦げる程度まで強力に焼く処理)【11,115,126】。樽の加熱処理により、リグニンやタンニンの分解が促進されバニリンやフェノール類の生成が増えるため、ウイスキーにより甘くスモーキーな香味が付与される【112,115】。また、形成された活性炭の層は一種の触媒・吸着剤として働き、不要な成分(特に硫黄化合物)の一部を除去するとともに、リグニンやヘミセルロースのさらなる分解を助ける【7,11,112,127】。
熱処理で生じる化合物の種類と量は、加熱温度と時間に依存する。一般にライトトーストは約120℃で最大90分ほど、ミディアムトーストは120–230℃程度、ハイトースト(チャー)は230℃超の高温で15分以上行う【126】。強く長時間のトーストでリグニンの本格的な分解が始まり、フェノール類、芳香族ケトン類、アルデヒド類(例えばシリンガルデヒド、コニフェラルデヒド、バニリンなど)の濃度が高くなる(図8)【11,38】。エタノールはリグニン分解物の一部と反応し、コニフェリルアルコールやシナピルアルコールを生成する。これらはさらに酸化されてシナムアルデヒド類(コニフェラルデヒド、シナパルデヒド)になる【7,128】。シナムアルデヒド類は側鎖に二重結合を持ち、さらに酸化されてベンズアルデヒド類(バニリンやシリンガルデヒド)へと変化する【115,128】。これら芳香族アルデヒドは上質なスピリッツの指標成分とみなされており、その濃度は使用樽の種類や焼き加減(チャーの度合い)に依存する。樽材の種類と熱処理によって成分の溶出やリグニンのアルコール分解(アルコホリシス)の程度が変化するためである【126】。
一方で過度な加熱処理は、グアイアコールやシリンゴールのようなフェノール類の濃度を過剰に高める場合がある【11】。これらの成分は適量では心地よいスモーキーさや薬品的・スパイシーなニュアンスを付与するが、増えすぎるとウイスキーのフレーバーを圧倒し支配してしまう恐れがある。なお、オーク材への熱処理はラクトン(ウイスキーラクトン、γ-ラクトン)の溶出も促進する。ラクトン類は木材中の脂質の熱分解によって生成する成分であり、熟成ウイスキーにココナッツ様の甘い香りを与える。
5. コンジナーの偽装検知および真正性確認への活用
コンジナーの同定はブランド保護の目的に寄与するだけでなく、ウイスキーの風味形成に深く関与する主要成分を分子レベルで理解することにもつながる【7】。前述の通り、コンジナーのプロファイルは原料と製造プロセスの積み重ねである。このため、コンジナー分析によってブランドや蒸留所、ウイスキーの種類/スタイルに特有な特徴を分子レベルで見いだすことができ、真正性(オーセンティシティ)の確認にも利用し得る。
コンジナーは揮発性か非揮発性かに大別される。揮発性コンジナーは極めて多種多様(濃度範囲も ng/Lからg/Lまで幅広い)であり、我々の嗅覚に大きな影響を及ぼす。一方、非揮発性(味覚に寄与する)成分は香りほど多様ではない【12,74】。コンジナーごとに揮発度、分子量、蒸気圧、極性といった性質は異なり、そのため抽出や分離のしやすさにも差がある【143】。ウイスキーのコンジナー分析にはもっとも一般的に**ガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)が用いられる【6,40,73–76,97,110,111,143–146】。GC-MSは幅広い微量成分の同定・定量を可能にし、多くの技術では検出困難な高い感度と網羅性を有している。しかし、揮発性成分と知覚される香りとの関連性を明確にすることは容易ではない。なぜなら食品や飲料では、揮発性化合物のごく一部のみが各々のにおい閾値を上回って香りに寄与しており、またそれらが相互作用する複雑な体系だからである【147】。鍵となる芳香成分(香気活性の高いコンジナー)を特定する有用な手法の一つにガスクロマトグラフィー-オルファクトメトリー(GC-O)**がある。これは分析機器の検出器に加えて訓練済みパネル(人間の嗅覚)を用いる手法であり、どの成分が香りに影響しているかを評価できる【148】。GC-Oは香りに関与する成分すべてを完璧に明らかにできる手法ではないものの、個々の芳香コンジナーの影響度合いをより良く評価する助けとなり、嫌な臭い(オフフレーバー)の検出にも有用である【149】。
スタイル/タイプ間の差異を示すユニークな化合物を評価するだけでなく、一部の特定コンジナーの濃度比に着目してウイスキーの真正品/偽物判別を行う試みもなされている【7,11,40】。複数の原料穀物や蒸留・熟成技術を用いて作られるブレンデッド・ウイスキーは、その構成比率の違いによって成分が大きく変動するため同定・比較が難しいが、特定成分の比率や範囲を指標とすることで識別が試みられている。具体的には、トウモロコシ・コムギ・オーツ麦・未発芽大麦・モルト大麦といった各原料が多く使われた場合に特徴的となる成分の割合を検証し、その比率から製品の真偽を推定するアプローチである【7,8,11】。
中でも高級アルコール類は、ウイスキーの地域・スタイルを区別する指標として古くから利用されてきた。例えば2-メチルプロパノール(イソブタノール)、2-メチルブタノールおよび3-メチルブタノール(イソアミルアルコール)の3種の高級アルコールは、ブランド、地域、スタイル/タイプの識別にしばしば用いられる【3,5,8,15】。グレーンウイスキーでは連続蒸留の効率が高いためこれら高級アルコールの濃度が低く抑えられる傾向がある。したがって、一般にグレーン主体のウイスキーには1-プロパノール(プロピルアルコール)とイソブタノールが相対的に多く、モルト主体のウイスキーにはイソアミルアルコール(3-メチルブタノール)と2-メチルブタノールが相対的に多い。ゆえに**(2-メチルブタノール + 3-メチルブタノール) / 2-メチルプロパノール比**を算出すると、その値によって原料や蒸留方法の違いをある程度推定でき、スタイルやタイプの識別に有用である【11】。ただし、2-メチルブタノールと3-メチルブタノールの比率のみでは銘柄間で大きな差が出ないことも多く、高級アルコール濃度自体は異なっても比が似通ってしまう場合があるため、この2成分比のみの判別法はあまり効果的でない【7】。一方、ブレンデッド・ウイスキーにおいて2-メチルブタノールと3-メチルブタノールの含有量が高い場合、それはモルトウイスキーの比率が高いブレンドであることを示唆する【8,150】。高級アルコール類は混和原酒の比率を反映するマーカーと言える。
分析の観点では、伝統的にアイリッシュウイスキーはスコッチに比べて香味成分のマトリックスが単純であると見なされてきた。スコットランドとアイルランドは地形や気候が類似しているため、この差異は両国の蒸留方式の違い(アイリッシュは伝統的に三回蒸留が多い)に起因すると結論づけられることが多かった【7,8,23,74,151】。しかし既に述べたように、現在では全てのアイルランド産ウイスキーが三回蒸留というわけではなく、新興のアイリッシュ蒸留所の多くは風味を重視して二回蒸留のみを採用している。スコッチシングルモルトとブレンデッドの比較研究では、多数のスコッチ製品を比較し幾つかのコンジナーが識別指標として用いられてきた。例えばフェノール類は異なるウイスキーの識別において重要な指標成分になり得ると考えられる。また、ある研究ではオイゲノール(丁香油成分、スパイシーなクローブ様香気)がバーボンを識別する有用なバイオマーカーであると示唆されている。オイゲノールはバーボンでは他のウイスキーより一貫して高濃度で存在するためである【8,77】。新造スピリッツ(熟成前のニューメイク)と熟成後のウイスキーを比較し、木材由来成分の寄与を特定した研究もある【109】。中には、熟成期間(製品の熟成年数)によって濃度が増加する成分を見出し、エイジングの指標になり得ると報告した例もある。例えばある揮発性エステルはワインとスピリッツの熟成の双方で濃度が上昇することが確認され、熟成度合いのバイオマーカーとなり得ると指摘されている【74】。
揮発性コンジナーによる熟成段階(新造 vs 熟成)の区別は時間要因が大きいが、一方で新造スピリッツ(ニューメイク)に着目することで製造初期段階、とりわけ穀物原料・発酵・蒸留の差異に起因する成分をより多く解明できる可能性がある【7,71,126】。実際、熟成段階に関連するコンジナー(例えばバニリンやラクトン類)は真正性検証や熟成条件差の判別に活用されてきた一方で【110,111,155,156】、異なる発酵条件や原料による香味変化に着目した研究も行われている。後者は識別・鑑別の目的というより、実験的に発酵条件を変えることでユニークな香味プロファイルを持つウイスキーを生み出し、それを真正性のバイオマーカーとして利用できる可能性を示すものである。具体的には、異なる酵母種の使用、麦汁前処理の変更、発酵時の細菌の影響、新造スピリッツの穀物(例えばコムギ)原料化などの効果を調べた研究が報告されている【1,27,54,75,86,157】。
補足表8: ウイスキー鑑定に利用される主要コンジナーおよび指標
| コンジナー/指標(比率など) | 示唆するもの・用途(真正性/品質評価への利用) |
| 高級アルコール比(2-メチルブタノール + 3-メチルブタノール)/ 2-メチルプロパノール | モルト系原酒比率の指標。グレーン主体の製品ではこの比が低く、モルト比率の高い製品では高い【11】。ウイスキーのスタイルや原料組成を推定する手がかりとなる。 |
| フェノール類含有量(グアイアコール、フェノール他) | ピーテッド麦芽の使用指標。フェノール量はアイリッシュよりスコッチで高い傾向【28】。地域・製法による違い(ピート香の有無)や、ピーテッド/ノンピーテッド製品の判別に利用される。 |
| オイゲノール (クローブ様フェノール) | バーボンのバイオマーカー候補。バーボンでは他のウイスキーよりオイゲノール濃度が一貫して高いため、スタイル鑑別や真贋判定に利用可能と報告【8,77】。 |
| バニリン濃度 | 樽熟成由来の芳香成分。正規品ウイスキーは木材由来バニリンを含むが、偽装品は市販フレーバー由来のバニリンを含む場合がある。市販品由来のバニリンは構造異性が異なることもあるが、何より濃度が極端に高い場合は添加を示唆するので検知に利用可能【154】。 |
| 芳香族アルデヒド類(シリンガルデヒド、コニフェラルデヒド等) | 樽材由来の芳香成分であり、熟成期間や樽種の指標となり得る。濃度が高いほど長期熟成・重度チャーを示唆し、「良質なスピリッツの指標成分」とも言われる【126】。ブランドや製法の違いを評価する上で注目される。 |
6. 結論
ウイスキーは、その原料、製造工程、熟成プロセスの変化によって生まれる多様なフレーバープロファイルを持つ複雑な製品である。特に発酵と樽熟成はコンジナーの生成と変化において重要な段階であり、フレーバー形成や真正性評価の観点からこれまで最も多く研究されてきた。また、分析装置と手法の感度・性能が向上し続けることで、香味特性の差異を生み出すコンジナーや、真正性のバイオマーカーとなり得る成分に関する情報は飛躍的に増えつつある。この傾向は今後も継続し、品質評価や不正検知のための迅速で非破壊的な分析手法の発展と歩調を合わせて進むだろう。
世界的な蒸留酒ビジネスとして確立されたウイスキーであるが、他の飲料や食品に比べるとコンジナーの詳細なプロファイリング研究はまだ十分とは言えない。ウイスキーの真正性に関するこれまでの研究の多くは、比較的少数のサンプルを用いて行われており、それらが代表するスタイル/タイプの特徴とされているに過ぎないケースもある。そのため銘柄内・銘柄間のばらつき(変動性)を十分に考慮できていないことがあり、実際には原料や製法等の多様な要因によるコンジナープロファイルの変動が見落とされている可能性が高い。したがって、ウイスキーのフレーバープロファイルに関するより詳細な研究が今後さらに必要とされる。
現在、アイルランドのウイスキー産業は急速な拡大期にあり、新規蒸留所と既存蒸留所の双方が、競争市場で独自かつ正統的な製品を提供して市場拡大を図る必要に迫られている。特にアイルランド産ウイスキー業界は、人気と市場拡大が進む中で以下のような大きな課題に直面している。(i) 樽熟成のオプション多様化やブレンディング手法拡充による製品多様性の飛躍的増大; (ii) シングルポットスチル・ウイスキーの成長とそれに伴うマッシュビル(原料配合)の進化; (iii) 複数蒸留所から供給される長期熟成原酒の増加に伴うプレミアム化の進展、である。このような状況下、これらの多様性を科学的に捉え管理すること、および真正性を担保しブランド価値を守ることが、今後一層重要になるだろう。
著者貢献: コンセプト立案 – K.N.K.およびC.O.; 調査 – T.J.K., K.N.K., C.O.; ライティング(原稿作成) – T.J.K.; ライティング(レビュー・編集) – K.N.K., C.O.; スーパービジョン – K.N.K.; プロジェクト管理 – K.N.K.; 資金獲得 – K.N.K.
資金提供: 本研究はTeagascのプロジェクト1376「アイリッシュウイスキーの真正性を検証し不正を防止するバイオマーカーの特定」および関連するWalsh奨学金「ウイスキーのコンジナー分析 2021057」によって資金提供を受けた。
謝辞: Teagasc食品研究センター(アイルランド・コーク県ファーモイ、Moorepark)のフレーバー化学施設の同僚から得られた支援に感謝する。
利益相反: 利益相反はないことを著者一同が宣言する。資金提供者は研究の設計、データ収集・分析・解釈、論文執筆、また出版決定に何ら関与していない。